「手足の感覚が鈍くなったような気がする」「手足がしびれる」
「皮膚がピリピリする」「蟻が這っているようで気持ち悪い(蟻走感:ぎそうかん)」
これらは更年期に起きやすい症状です。
なぜこのような症状が起きるのでしょうか?その原因と緩和する方法、さらに更年期症状ではなく他の病気の可能性について紹介します。
更年期のしびれ・こわばりはエストロゲンの減少が原因だった
だれでも年齢を重ねるとシワが増えたり乾燥肌になってきます。いつまでも若くありたいと願う女性にとっては、美容面での変化も深刻です。
悲しいことに、女性の場合加齢と共に徐々に変化していくのではなく、更年期にガクッと潤いがなくなっていきます。
それは女性ホルモンのエストロゲンが急激に減少していくからです。
エストロゲンの減少によって皮膚が薄く弾力がなくなる

エストロゲンには皮膚に弾力や潤いを与えて若々しく保つ作用があります。エストロゲンが減少すると老化が進んで皮膚が薄くなり、皮脂や水分も減ってきます。
そうなると、皮膚の弾力がなくなるだけでなく、刺激にも弱くなってしまうのです。些細な刺激にも敏感に反応するようになり、しびれまでは感じなくても違和感を感じるようになります。
また、自律神経の乱れもこうした知覚の異常に関係しています。エストロゲンと自律神経の関係はこちらの記事を参考にして下さい。
関節の不調はエストロゲンの減少も要因
関節の痛みは、関節をスムーズに動かすための軟骨が擦り減ったり筋肉が衰えることで起こります。いつも同じ姿勢や動きをしていたり、スポーツによって酷使することによって起こりますが、エストロゲンの減少が原因のこともあります。
更年期の関節痛の多くは、こうした軟骨や筋肉の老化に加えて、エストロゲンが減少して血行が悪くなることも要因となっています。
この症状は、女性ホルモンが不足してきた初期に感じる人が多く、手首やかかと・指など小さな関節のこわばりやしびれから感じ、次第に膝や股関節など大きな関節の痛み、腰痛へと移っていきます。
油断しないで!更年期障害以外の原因のことも!
そうはいっても、こういった手足のしびれや関節痛がすべて更年期の症状だと油断していると、思わぬ病気が潜んでいる可能性もあります。
同じような症状が起こる病気には関節リウマチなどの自己免疫疾患や脳の病気でも手足のしびれを感じることがあります。更年期の症状と間違いやすい病気をいくつか紹介します。
女性に多い関節リウマチ
関節痛といえばリウマチでは?と思い浮かぶほど知られている病気ですね。この場合正確には「関節リウマチ」です。
病気のくくりはややこしくて、ちょっとわかりづらいので簡単に説明します。
関節リウマチは、関節が炎症を起こし、次第に軟骨や骨が破壊されて変形してしまう病気です。原因は免疫の働きの異常と考えられています。
生物には外的から守るはずの免疫が備わっています。それが自分自身の細胞やタンパク質を攻撃してしまうのが自己免疫疾患です。関節リウマチは自己免疫疾患に分類されます。
一般に関節リウマチはリウマチと言われますが、広い意味でのリウマチは関節や周囲の骨、筋肉などが痛む病気全般を指し、これをリウマチ性疾患といいます。
- 自己免疫疾患(関節リウマチ・全身性エリテマトーデスなど)
- 細菌やウイルス感染によるもの
- 代謝の異常(通風、甲状腺の病気など)
- 外傷や加齢によるもの(変形性関節炎など)
- ストレスなどによるもの(慢性疲労症候群など)
関節リウマチ発症のピークは30~50代!女性は男性の4倍!
関節リウマチはどの年代でも起こりうる病気ですが、発症は30代~50代がもっとも多く、全体で見ても女性は男性の4倍です。プレ更年期から更年期真っ只中の女性が要注意な理由です!
もともと自己免疫疾患は女性に多い病気です。関節リウマチを含む膠原病ではさらにその差は開き、圧倒的に男性より女性が多いほどです。10倍以上といわれます。
膠原病も最近よく聞かれる疾患ですね。膠原病とは、皮膚や血管、筋肉、関節など全身にある結合組織に慢性的に炎症が起こる疾患です。
実は病名ではなく、ある特徴を持つ疾患の総称で、グループ名という感じのものです。
こちらもまたややこしいのですが、結合組織に病変を持つ疾患のひとつが膠原病と呼ばれる疾患グループなのです。膠原病と関節リウマチを図解するとこんなかんじです。

重症化すると寝たきりにも!繊維筋痛症
繊維筋痛症とは、検査をしても血液にも、免疫にも異常が認められないのに、全身激しい痛みに襲われる病気です。
痛みの程度は軽度~重度まであり、重度になると「ガラスの破片が通ったような」と形容されるように、まさに激痛です。
重症の場合、髪や爪に触るなどの少しの接触や温度湿度の変化にも反応して疼痛が走り、日常生活も困難になってしまうこともあります。
全身または広範囲に痛みが拡がることもありますが、関節などある部分だけ痛む場合もあります。また、部位も日によって変わったりもします。
発症は男性より女性、特に中高年の女性に多いと言われています。
まだ認知度が低く、自律神経失調症や更年期障害など誤診されることも。推定では200万人の患者がいるのではといわれています。
中高年女性に多い手のしびれは手根管症候群だった!?

手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)って聞いたことありますか?
手根管とは手首にある骨と靭帯で囲まれた空間で、9本の指を動かす腱と正中神経が通っています。
ここがなんらかの理由で圧迫されることによって、手のしびれを感じるようになります。これを手根管症候群といいます。
外傷によるものや代謝性疾患に起因するものもありますが、ほとんどが手を酷使したことによる髄膜炎と更年期の女性の特発性の症状です。この場合、原因はよくわかっていません。
症状の特徴として、小指と薬指の半分(小指側)にはしびれを感じないことです。重症になると親指の付け根の筋肉が萎縮して筋力低下や開かなくなるなど、日常生活に支障をきたします。
頚椎や腰椎の変形でも手足のしびれや麻痺はおこる
だれでも加齢に伴って椎間板は老化していきます。椎間板は頚椎同士のクッションの役目を果たしています。クッションがつぶれることによって、骨がだんだん大きくなって棘々してきます(骨棘=こつきょく)。
また、こちらもやはり加齢によって靭帯が厚く固くなります。これらが原因で脊髄管にある脊髄が圧迫されて手足にしびれや運動障害があらわれます。
手足の先からピリピリじんじんは糖尿病が原因!?
糖尿病の合併症には三大合併症とよばれるものがあります。
- 糖尿病性網膜症
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性神経障害
この糖尿病性神経障害では、初期症状として手足の先の痛みやしびれがみられます。放っておくと末梢神経が破壊され、感覚が鈍くなったりなくなったりします。

まとめ
急に手足がしびれたり関節が痛んだりすると誰でも心配になります。特に指先の感覚が変だと、家事をするのも気が滅入ってしまいますね。
それに、関節痛もなかなかしんどいです。私もエストロゲンが急激に減ってきたかな-という時期、とても辛かったのを覚えています。
朝起きてしばらくは手足がこわばってキッチンに立つのも嫌でした。それどころか、歩くのも・・・。
でも、その痛みやこわばりは自然に軽減していきました。手足のしびれや違和感、関節痛は更年期の症状であればそれほど心配しなくても大丈夫です。
ただ、症状が次第に重くなっていくときや、あまりに長期間続くときはこの記事でも紹介した他の病気の可能性もありますから、専門機関を受診してくださいね。
更年期障害の場合は血流をよくすることが症状緩和には効果的です。しっかり入浴をする・マッサージをするなどして血行を促進しましょう。
- 更年期の体の不調の原因と対策
- 更年期障害 / 手足のしびれ / 関節痛
- コメント




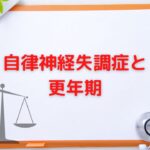




 更年期でホットフラッシュがつらいわ・・・という人も、実は冷え症になっているかもしれません。自覚症状のない人でも、
更年期でホットフラッシュがつらいわ・・・という人も、実は冷え症になっているかもしれません。自覚症状のない人でも、




